看護学校を卒業し、新人看護師として入職すると、最近ほとんどの病院ではプリセプター制度が整っており、プリセプターがあなたの教育担当となります。
しかし、病院によっては、プリセプターがいない職場もあります。
プリセプター制度がない病院の理由としては、
- 看護師の人員不足のため
- 教えられる人材(看護師)が不在のため
- プリセプター制度は必要ないと判断されている病院のため
など、様々な諸事情が考えられますが、一般的に新人看護師にとっては、プリセプターがいてくれた方が、安心できる面も多いと言えるではないでしょうか。
私は、看護学校卒業後、新卒看護師として病院に勤務し、入職して初めて「プリセプターがいない」ことが分かりました。(今思えば情報収集が不足していたと感じます。)
しかし私は現在、看護師として14年目であり、(立派に)職務を遂行しています。
この経験から、実際にプリセプターがいない病院に新卒・新人看護師として入職した際に困ることを中心に対処方について、説明していきます。同じ境遇の方は、是非参考にしてください。
1.プリセプターがいない場合の教育は誰が行う?

画像:shutterstock
プリセプターがいない病院というのは、プリセプターの必要性の有無について、明確な根拠に基づいて廃止しているところ以外、ほとんどの場合は、人員不足や忙しすぎて教える看護師がいないなどの複雑な理由があります。
新人が入ってきても「誰が教えるの?」というような譲り合いとなります。
そのため、新人看護師の教育は、結局日替わりで先輩看護師について歩き、仕事を覚えていくことになります。
対処法:自分を信じて頑張ろう
プリセプターがいないため、様々なトラブルが起こる可能性があります。
ただ、ないものねだりをしても始まりません。そのため、以下のことを心に刻んでください。
- 自分を信じること
- 仕事を頑張ること
- やる気を出すこと、見せること
- 勉強や努力を怠らないこと
- 諦めないこと
- 気持ちを切らさないこと
- ポジティブに考えること
- 自分は自分で守ること
おそらくプリセプターに言われる言葉であり、新人看護師がフォローされることです。
プリセプター制度があるために、対応や人間関係に悩み苦しむ新人看護師も存在するため、「プリセプターがいない」ということをまずはポジティブにとらえて仕事に励むことが重要です。
私の体験談
私は結果的に、プリセプター制度がない病院に勤務して良かったと考えています。
理由としては、「教育されるのは当たり前」という感覚を多くの看護師が持っている点です。
新卒看護師の場合などは理解できますが、看護師としてのキャリアが3年以上ある方でも、新しい仕事を始める際に、教えてもらって当たり前という感覚が多くあるように感じます。
看護師としての仕事の幅が今後広がることを考えると、「自分で学ぶ力をつけること」「教育されるのはありがたいと思うこと」「教えてもらえることに感謝を伝えること」が分かっているほうが、スムーズに仕事が取り組めると思いますし、社会人としては当たり前だと私は考えています。
そのため、今は苦しいかもしれませんが、私は長い看護師人生を考えると結果的に良かったと感じています。
各先輩で教え方が変わり内容も違う

画像:shutterstock
私の場合、プリセプターがいない中で、仕事を教えてもらう必要があり、基本的には日替わりで新人担当が変わりました。
また、そうでない場合でもプリセプター制度がないために、教えてくれる先輩看護師の責任感が薄く、教え方も丁寧ではない場合もあるのではないでしょうか。
当時の私は、それに対して意見することもできず、素直に謝ることしかできませんでした。そして私は「あの新人看護師はできない」という印象を与えていましました。
このようなことにならないために、対処法を説明していきます。
対処法1:まず1番に相談できる先輩看護師を見つける
プリセプターがいない環境でも、必ずその日の新人担当の看護師がいるはずです。
必ず新人看護師を気にかけてくれる先輩はいるはずであり、その全ての先輩看護師が頼りにならない訳ではないはずです。
その先輩を頼りにし、困ったことがあったら、自分から積極的に相談するようにしてみましょう。
対処方法2:技術面は、信用できる先輩に確認してもらう
技術面については先に述べた通り、先輩看護師によってやり方が少しずつ違ってきますので、先輩によってやり方が違った点や、疑問に感じたところはメモを取りましょう。
また、実践する際は信頼できる先輩看護師の方に「〇〇をやりたいのですが、できているか確認してもらって良いですか?」という感じでお願いしましょう。
ここでも、「わざわざ私のために教えてもらっている」という気持ちは大切です。
日々のフィードバックがない

画像:shutterstock
プリセプターがいないということは、日々のフィードバックを一緒にしてくれる先輩もいないので、その日に分からなかったことなどは質問できず、たくさんの疑問を抱えたまま家に帰る場合も多いのではないでしょうか。
このような場合、分からないまま翌日に看護業務を行い、「できていない!」と注意を受ける日々となる可能性があります。
当初、誰に頼って良いのか私は本当に困りました。その体験から対処法を説明します。
対処法:その日に行ったことは必ず振り返り、分からないことは翌日質問する
日々のフィードバックがなくても、1人で1日を振り返ることは可能です。
そのため、その日1日に行ったこと(技術面の手順なども)必ずメモを取り、家に帰ってから、綺麗なノートにまとめ直します。(絵を描いてまとめるのも良いと思います。)
ノートにまとめているうちに、疑問点が出てきますので、翌日に、先輩に質問してから仕事を開始するように心がけてください。
私の体験談
私は、1人の先輩看護師が「何か困ったことはない?」と声をかけてくれ、その先輩には色々と質問することができたので、本当に助かりました。
しかし、自分で振り返りをしていなければ、「質問する内容も分からない」となるため、積極的に自分で学ぼうとする努力は必要といえます。
新人看護師(私)の情報共有をしていない

画像:shutterstock
プリセプターがいない、私が勤務した病院では、プリセプター会議のようなものはなく、新人看護師(私)の各種の習得状況のすべてを把握している人はいませんでした。
そのため、仕事中に知らないこと(教えてもらっていないこと)まで要求されることもよくありました。
また運悪く私の場合は、忙しい病棟だったためか、先輩もピリピリしており、とりあえず「分かりました」と返事をして、後から優しい先輩のところへ行って教えてもらいながら、行っていました。
このような場合の対処法を説明していきます。
対処法:できないことはできないとはっきり言う
優しい先輩ならば、「〇〇(技術)はもう教えてもらった?」などと確認してくれますが、確認もしてくれずに「行ってくるように」と頼まれてしまうこともあります。
そのような場合、必ず「まだ、できません。すみません、分からないので教えてください」など、自分の状況を積極的に伝えましょう。
自分の身を守るためでもありますし、何より患者が困ることになるので、気をつけましょう。
「教えてもらっていない」という言葉は使わないようにすることで、先輩看護師から教えてもらいやすくなるでしょう。
誰にも相談できない

画像:shutterstock
私の場合、その病棟に配属された新人は私1人だけだったので、同期同士で支え合うことができずに辛いこともありました。
そのため、業務内容だけでなく、日々の仕事上での先輩看護師との関わりなどで悩む時に「誰にも相談ができない」ということが精神的にも厳しかったことを覚えています。
対処法:自分なりの努力と仕事を覚えること
このような場合の対処法としては、
- 友人に相談すること
- 自分なりに努力をすること
- 早く仕事を覚えること
上記のことを行っていれば、辛い状況もいつまでも続くわけではありません。
理由としては、先輩も認めてくれるようになり、数ヶ月経った頃には多くの先輩とコニュニケーションが取りやすくなります。
また、信頼できる先輩に色々と相談できるようになり、少しずつ環境が変わっていくでしょう。
プリセプターがいなくて辛いと思いますが、自分を信じて努力しましょう。将来的には良い経験だと思える日が必ずきます。
最後に
新人看護師にとってプリセプターがいないということは、どうやって仕事を覚えていけば良いのか、誰に相談したらいいのか、など不安を感じると思います。
しかし、今では環境が整っている場合が多いですが、プリセプター制度がない時代を過ごしてきた先輩看護師も沢山存在することは事実です。
だからこそ、今の新人看護師が、プリセプターがいなければ成長できないという訳ではないと、私は思います。
そのため、プリセプターがついていない新人看護師の皆さんは、とても大変だと思いますが、「必ず成長できるのだ」と自信を持って仕事してください。



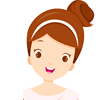
コメント