大学病院は、様々な検査や手術を受ける患者がいるため看護師として経験できる幅が広く、忙しいことが多いですが、他の病院では経験できない疾患や検査について経験できるなど看護師のスキルを積むことができると感じています。
今回は、一般の病院と比較し、大学病院の看護師が忙しい理由を私が勤務していた体験談から説明していきます。
患者数が多い

画像:shutterstock
大学病院は、規模が大きく病床数が非常に多いため、必然的に患者数も多くなります。入院患者が多い分、看護師1人あたりが担当する患者数も多くなり、行う看護も増えるため、忙しく感じます。
特に日勤だと患者の状態観察・検査・点滴・日常生活のケア等、1人の患者に対して1日の勤務中に行うことがとても多く、病院の面積が広いため検査やリハビリの送迎だけでも時間がかかり病院内を1日中忙しく動き回ることもあります。
緊急入院が多い

画像:shutterstock
大学病院では、日勤・夜勤を問わず緊急入院が非常に多いですが、それは「救急搬送を受け入れる病院が限られているため(地域にもよります)」ということがあり、必然的に大学病院に送られ、看護師は忙しくなります。
「今日は手術等の大きなイベントがない」と思っていても緊急入院する患者がいるため、急に忙しくなる場合があります。
外科の場合でも、緊急入院してすぐに緊急手術ということもあり短い時間で色々な準備を行うことが必要であるため、非常に忙しいです。
急変する患者が多い

画像:shutterstock
大学病院の患者は、難しい病態の患者や術後・末期状態の患者が多いため、急変することがよくあり何人もの医師や看護師がその患者に付きっきりになります。
急変する患者が多いと、必然的に看護師の忙しさも増します。
急変患者の担当外の看護師は「急変患者の担当をしている看護師の他の仕事をフォロー」をすることが必要で、自分の仕事以外を急に任されることも多いため、仕事量は増加します。
外科では手術が多い

画像:shutterstock
大学病院の外科の場合、手術が多いことも看護師が忙しい理由の1つとしてあります。外科の場合、毎日のように何件もの手術が行われることもあります。
そのため手術後の患者の担当看護師は、
- 手術前の準備
- 術後の頻回の状態観察
- 量の多い点滴
等を行うことが多く頻回の訪室が必要であるため、時間を要します。
勉強会などが多い

画像:shutterstock
病棟看護師による勉強会だけでなく、
- 「病院全体の勉強会」
- 「システムの説明会」
- 「委員会」
など規模が大きい大学病院ほど絶対参加しなければいけない勉強会等が非常に多くなります。
参加必須の勉強会・説明会・委員会は、休みの日でも参加することを強制される場合が多いため、休日に出勤する場合もよくあります。
勉強会等は、基本的に日勤帯の終了時間後に行うことが多いため、忙しくて仕事がまだ残っている状態でもそれに参加するため、一旦仕事を中断して参加し、終了後に残業して仕事を再開する場合もあります。
他職種との連携が多い
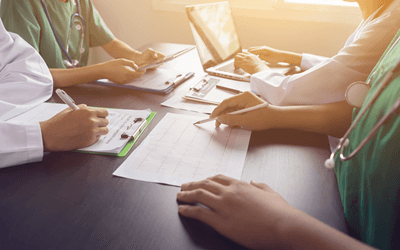
画像:shutterstock
大学病院では、援助が必要な患者が退院する場合、退院後の生活について他職種との連携を行う場合があります。
援助が必要な患者の退院後の生活について連携する職種としては、
- 医師
- 栄養士
- 薬剤師
- リハビリの訓練士
- 医療ソーシャルワーカー
等があります。(患者の状態によって連携の職種は異なります。)
大学病院が他職種と連携する場合、必要な全ての職種を集めて話し合いをする際の連絡役・資料作成・記録の記載など、患者の1番そばにいる看護師が行うことが多いため、日常の業務以外の業務を行うこともよくあります。
最後に
大学病院によっては、看護師の体制が整備されている病院もあり、働きやすさを感じる看護師もいるのかもしれませんが、やはり一般病院の看護師と比較すると忙しいことが挙げられます。
大学病院への中途採用を希望する看護師の方は、看護師が働くメリットやデメリットなどもしっかりと確認の上、転職活動を行ってみてください。




コメント